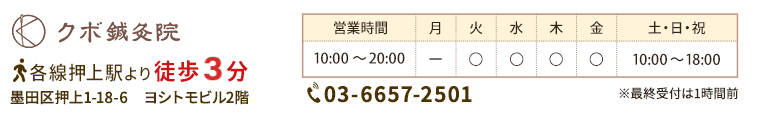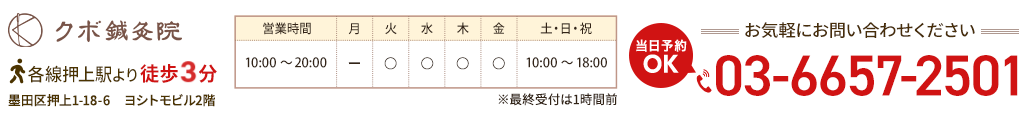過敏性腸症候群(IBS)
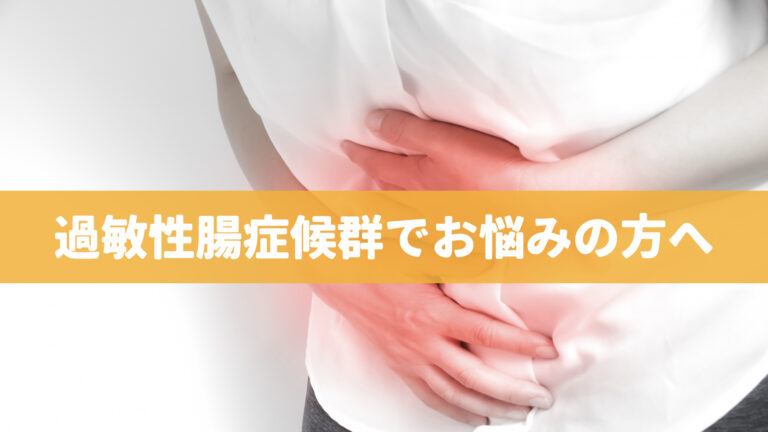
- 通勤や通学途中にお腹が痛くなる
- 電車での移動が毎日不安
- 会議前には必ずトイレに行く
- 下痢や便秘を繰り返す
- 人前に立つ機会があると腹痛やガスがたまる
︎過敏性腸症候群の定義
- 排便と症状が関連する(トイレにいけば症状が軽減するなど)
- 排便頻度の変化を伴う(トイレに通う頻度に増減がある)
- 便状の変化を伴う(便の外観が変わったり、
硬さが変わったりする)
︎西洋医学的な原因
- 食物不耐症
- ストレス
- 感染
- 内臓痛覚過敏
- SIBO
- 腸内フローラ
食物不耐症とは特定の食品を分解する酵素が欠損している状態のこと。
例えば、牛乳やヨーグルトなどの乳製品、ソーセージやハムなどの加工肉、グルテン、果糖などが挙げられます。
︎東洋医学的な原因と鍼灸治療
■ 過敏性腸症候群になりやすい人の特徴
・力が抜きにくい
・人にすごく気を使う
・爪が脆くなりやすい
・手足や脇に汗をかきやすい
・ガス溜まりでお腹が張る
・元々胃腸が弱い
・大きい音や怒鳴り声が苦手
・昔から便秘もち
・気圧の変化で偏頭痛になる
・考え事が多く不安感も強い— クボ先生│鍼灸師 (@kubo_tubo) March 5, 2023
もしあなたが上記の項目に7つ以上当てはまるようであれば、東洋医学的なアプローチが必須と言えるでしょう。
その理由をここから解説していきますね。
過敏性腸症候群の分類
私の臨床経験では過敏性腸症候群の原因は下記の4つに分類します。
- 血行不良
- 熱こもり
- 感覚過敏
それぞれ解説していきますね。
①血行不良
血の巡りが悪く腸に必要な栄養が行き届いていない状態です。
その他の症状は下記のとおり。
- 爪が脆い
- よく足をつる
- 末端冷え性
- 緊張すると脇汗をかく
- 首肩こりが酷い
- 目の奥が痛む偏頭痛
- 生理痛が重い
- 下半身のむくみ
- ガスが溜まりやすい
- 内腿を揉むと圧痛がある
- 足に糸ミミズ状の毛細血管が浮き出る
腸の運動(収縮と弛緩)にも血の巡りは重要です。
上記の症状も併発していれば血の巡りを良くする治療が必要となります。
鍼灸ではお腹の冷えがある場合は箱灸をしたり、末端のツボを用いて血流を改善していきます。
②熱こもり
慢性炎症やストレスによって体(腸)に熱がこもりやすい状態です。
その他の症状は下記のとおり。
- 逆流性食道炎がある
- 運動しても汗をかきづらい
- アレルギー性鼻炎
- 夏(暑さ)に弱い
- 顔面部に熱がこもる
- 頭痛を頻繁に引き起こす
- イライラしやすい
- 寝つきが悪い
- 喉が乾く
- 口臭がある
熱がこもると自律神経が乱れて腸の運動に悪影響を与えます。
鍼灸治療ではお腹周りの緊張を緩める、腸以外の症状を考慮して自律神経を調整する施術を行なっていきます。
③感覚過敏
皮膚や腸の粘膜が敏感で緊張と弛緩を繰り返す状態です。
その他の症状は下記のとおり。
- 服の繊維が気になる
- 一人の時間が好き
- ストレスに弱い
- 人にすごく気をつかう
- 怒鳴り声や大きい音が苦手
- 鼻炎を持っている
- 昔から朝が弱い
- 喘息やアトピーの経験がある
- お腹が張りやすい
- 呑気症(空気を飲み込みやすい)
まとめ

病院やクリニックで薬を処方されても一向に改善しない方は多いと思います。
東洋医学は腸だけにフォーカスするのでなく、体質や気質などに考慮し施術を行う医学です。
もしあなたが過敏性腸症候群でお悩みなら、東洋医学も選択肢の1つに入れてください!
必ず突破口はありますよ!